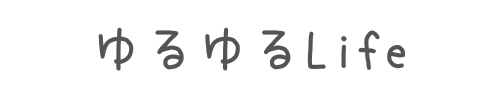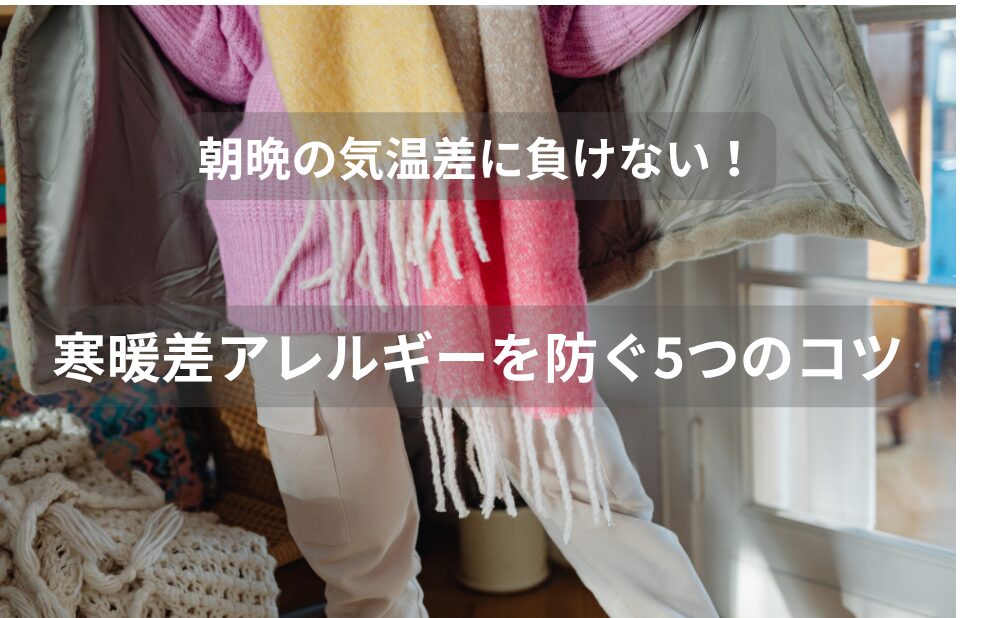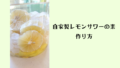春や秋の気温差が激しくなる季節になると、「鼻がムズムズする」「鼻水が止まらない」「くしゃみが連発」といった症状が出る人が増えます。私も毎年この時期には、鼻水がポタポタ…ティッシュペーパーが手放せなくなります。
花粉もないのに起こるこれらの症状は、「寒暖差アレルギー」かもしれません。
実は、正式には「血管運動性鼻炎」と呼ばれ、気温差によって鼻の血管が過剰に反応してしまう状態なんです。
寒暖差アレルギーとは?原因と仕組みを簡単に解説
寒暖差アレルギーの原因は、急激な気温変化によって自律神経が乱れること。
自律神経は体温を一定に保つ働きをしていますが、気温差が大きいと調整が追いつかず、鼻づまり・くしゃみ・倦怠感などが起こります。
花粉症との違いは、アレルギー物質が関係ない点。症状が似ているため、見分けづらいのが特徴です。
朝晩の気温差に弱い人の特徴とは?
寒暖差アレルギーになりやすい人にはいくつかの共通点があります。
たとえば、冷え性や低血圧、睡眠不足、ストレスが多い人。
また、エアコンの効いた室内と外気を行き来する生活もリスクを高めます。
中年以降の女性や高齢者は、加齢や運動不足により筋肉量が減って基礎代謝量が下がり、体内で産生できる熱が少なくなります。そのため症状がでやすくなるといわれます。
体温調節が苦手なタイプの人は、自律神経を整える生活習慣を意識することが大切です。
寒暖差アレルギーを防ぐ5つのコツ
コツ①:服装でうまく温度調整する
朝と昼の気温差が10℃以上ある日は、重ね着スタイルが基本。
薄手のカーディガンやストールで体温を調整しましょう。
首周り(手首、足首含む)を温めるのがおすすめです。

コツ②:室温を一定に保つ
寝る前や起床時の室温が急に変わらないよう、エアコンや加湿器で22〜24℃前後をキープ。
湿度50%前後が理想です。

コツ③:体を温める食事を意識
しょうが、ねぎ、根菜類など、体を内側から温める食材を取り入れることで、体温調整力がアップします。
スープにすれば、お野菜もたくさんとれて体にも嬉しいですね。

コツ④:お風呂で自律神経を整える
ぬるめ(38〜40℃)のお湯に10〜15分ほど浸かると、副交感神経が働いてリラックス効果が高まります。
好きな香りのアロマオイルを数滴落としての入浴もおすすめです。

コツ⑤:ストレスをためない習慣を
ストレスは自律神経の大敵。深呼吸や軽いストレッチ、好きな音楽などで、心の緊張をほぐしましょう。

症状がひどいときはどうする?受診の目安と対処法
鼻水が止まらない、頭痛や倦怠感が続くときは、耳鼻科を受診するのがおすすめです。
市販の抗アレルギー薬や漢方(小青竜湯など)で改善する場合もありますが、長引く場合は自律神経の乱れが原因になっていることも。
生活リズムの見直しも並行して行いましょう。
まとめ|朝晩の気温差に負けない生活を意識しよう
寒暖差アレルギーは、体が「環境の変化に疲れている」サインです。
特別な治療をしなくても、体を温める・規則正しい生活を送る・ストレスを溜めないことで十分に予防できます。
季節の変わり目を心地よく過ごすために、今日から少しずつ意識してみてください。